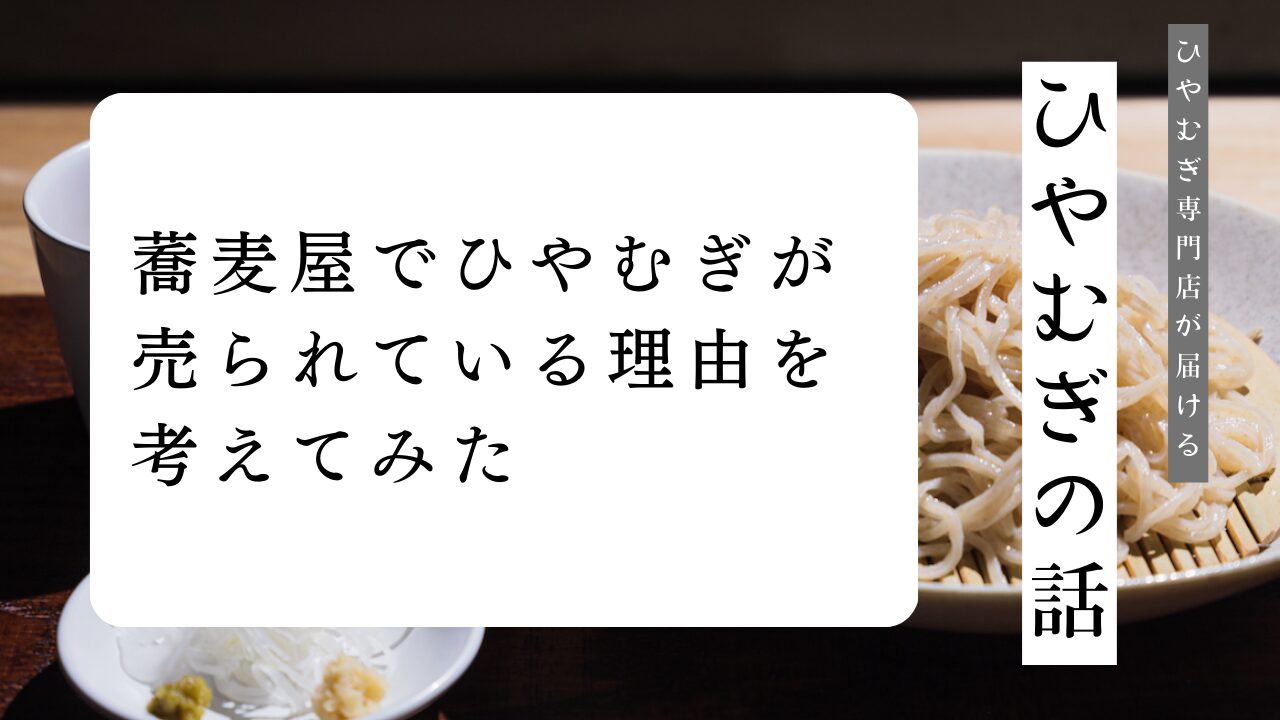蕎麦屋に行くと、たまに「ひやむぎ」がメニューにあることがある。
でも、よく考えてみるとちょっと不思議じゃないだろうか?
そうめんはあまり見かけないのに、ひやむぎだけは普通にメニューに載っていることが多いです。
これは偶然ではなく、きちんとした理由があるはずでは。
今回は、その理由をいくつか考えてみました。
1. 作り方の相性がいい
これは昨日のブログでも触れたけれど、蕎麦とひやむぎは作り方の相性がいい。
ひやむぎは小麦粉から作られる細めの麺だけど、蕎麦と同じように「切って作る」スタイル。
つまり、手打ち蕎麦の店でも対応しやすいし、機械打ちの店でも蕎麦と同じ設備で作れます。
例えば、もしそうめんを提供しようとすると、そうめんは基本的に「伸ばして作る」製法なので、専用の設備が必要になる。
その点、ひやむぎは蕎麦と作り方が似ているため、わざわざ別の道具を用意しなくても、蕎麦屋の環境に馴染みやすかったのではないでしょうか。
2. 昔から売られていたから
「なんとなく昔からあるものは、そのまま残り続ける」
これは、飲食店のメニューではよくある話ですね。
例えば、街の喫茶店で「ナポリタン」や「ミートソーススパゲッティ」が定番メニューになっていることが多いけれど、これは流行りというより「昔からあるから」残っているケースが多い。
蕎麦屋の「ひやむぎ」も、きっと同じ理由なのではないかと思うし、実際江戸時代の頃から蕎麦とひやむぎは一緒に売られていた可能性が高いです。
当時、江戸の庶民は蕎麦を好んで食べていたけれど、一方で小麦粉を使った麺類も身近な存在。
うどんの文化があった関西に比べると、江戸では小麦粉の麺を食べる機会は少なかったかもしれないが、それでも「冷たい麺類のバリエーション」として、ひやむぎは定着していたのではないか、ということです。
そして、一度定着すると、理由はあまり考えられずに「昔からあるものだから」として残っていき、現代の蕎麦屋でも同様にひやむぎを扱っているのかもしれません。
3. オペレーションの統一がしやすい
飲食店を経営している経験からもわかるけれど、オペレーションの統一はめちゃくちゃ大事。
特に麺類を扱うお店では、茹で時間の違いが意外と大きな問題になります。
例えば、
- 蕎麦とひやむぎは、茹で時間がほぼ同じ
- 一方で、そうめんは茹で時間が短い
これが何を意味するかというと、そうめんを茹でる場合は、タイミングをしっかり見ていないとすぐに茹で過ぎてしまう。
忙しい時間帯に注文が立て込むと、スタッフが「これは蕎麦? それともそうめん?」と混乱する可能性もある。
結果的に、そうめんはオペレーション上の負担が増える、ということです。
その点、ひやむぎは蕎麦と茹で時間がほぼ同じなので、同じように扱えるので、そういった心配がありません。
飲食店では、こうした小さな「手間の違い」が積み重なって、最終的に「どのメニューを残すか」という判断に影響を与えることが多いです。
だから、「オペレーションをシンプルにするために、ひやむぎが蕎麦屋で定着したのでは?」というのが、一つの仮説として考えられます。
個人的にはこのオペレーションの部分が、いまだにひやむぎからそうめんへ変えないことの理由なのではないかと思っています。
まとめ
蕎麦屋でひやむぎが売られている理由を整理すると、
- 作り方の相性がいい(蕎麦と同じように作れる)
- 昔から売られていた(歴史的な流れ)
- オペレーションが統一しやすい(茹で時間が同じ)
この3つの要因が重なったことで、ひやむぎが蕎麦屋の定番メニューとして残ったのではないかと。
逆に言えば、そうめんを蕎麦屋で見かけないのも、納得がいく話ですね。
次に蕎麦屋に行ったときは、ぜひ「なぜこのメニューがあるのか?」と考えてみると、さらに蕎麦屋に行くのが面白くなるかもしれないです。