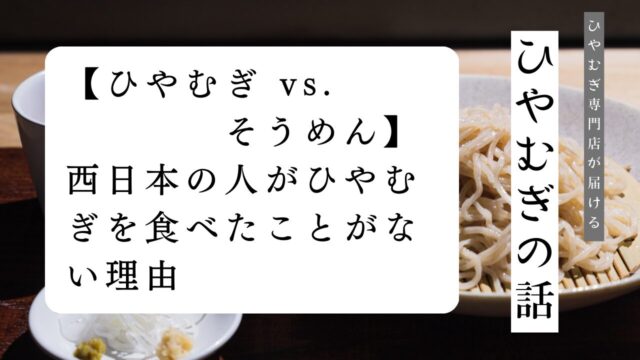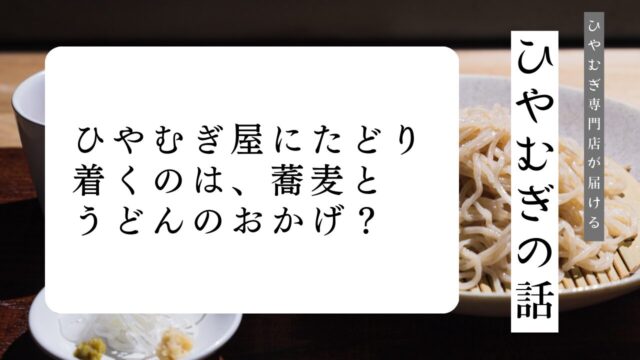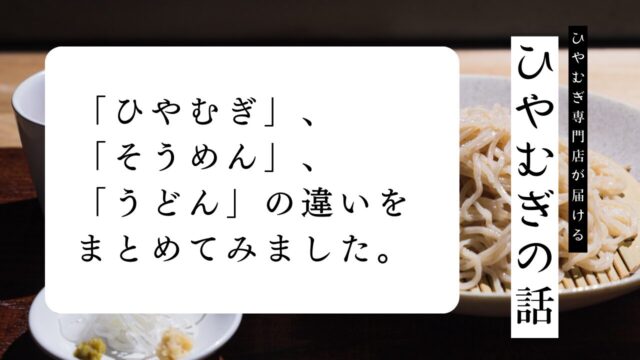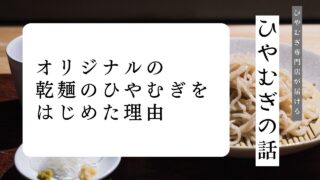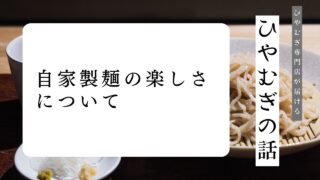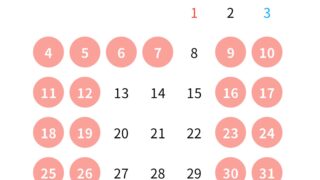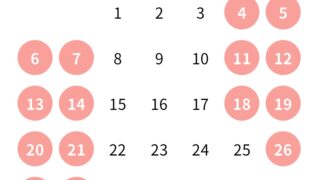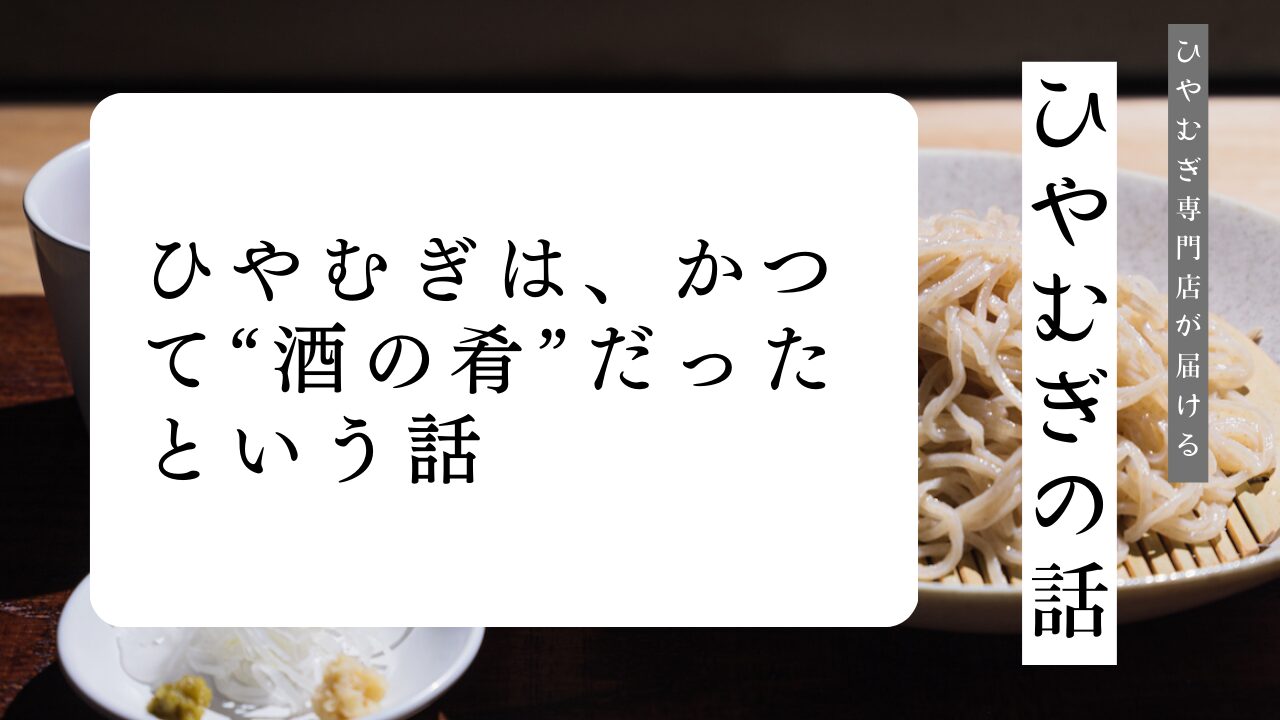
室町時代、ひやむぎはつまみだった
ひやむぎといえば、夏休みとかによく食べる麺料理。けれども、室町時代には驚くことに酒の肴として食されていたといいます。
現在のように主食として食べるスタイルではなく、小皿にちょこんと盛られ、お酒とともに楽しむ──そんな姿があったようです。
ひやむぎだけではなく、そうめんや蕎麦もまた、かつては「もてなし料理」として扱われていました。
現在のような日常食とは違い、特別な日や来客時に登場するごちそう。これらの麺は、ハレの日に食べる少し贅沢な一品だったのです。
粉ものは貴重な高級食材だった
当時の製粉技術や農業技術はまだ未熟で、小麦や蕎麦といった作物の収穫も限られていました。
そのため、小麦粉や蕎麦粉は高価で希少な食材。大量に麺を打って食べるというのは現代の感覚であり、昔は少しずつ丁寧に食されていたと考えられます。
一方でそんな粉もの文化が大きく花開いたのは江戸時代と言われています。
江戸時代になると製粉技術や農業技術の向上、そしてそれまで味噌がメインであった調味料が醤油へと変わっていきます。
鰹を干して長期間の保存性と旨みを両立させる、「枯節」という加工方法が確立していくのもこの時期。
こういった様々な技術が複合的に絡まり合って、日本の食文化に粉ものが大きな影響を及ぼすようになりました。
【特撰ひやむぎ きわだち】
東京都墨田区太平1−22−1 ソラナ錦糸町102
(錦糸町駅北口より徒歩8分、東京スカイツリーより徒歩14分)
12:00~15:00 18:30~21:00 (L.O.30分前 / 木・金はランチのみ)
火・水曜日定休
※席がハイカウンター6席のみのため、大人数や小さなお子様はご案内できないことがございます。
※ご予約はネット予約のみで、記載されている指定の時間及びコースのみのご予約となります。